
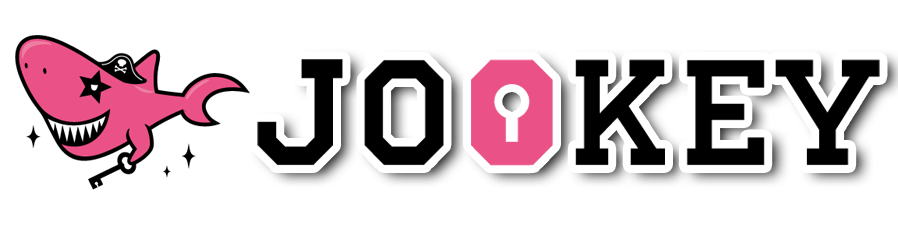


【第七話】墓地の住人
僕は、7年間墓地に住んでいた。
お笑い芸人を目指し、上京してまもなく、墓地生活は始まった。

賑やかな駅前を過ぎ、住宅街を抜け、しばらく歩くとさっきまでの喧騒が嘘のように、人の気配も人工的な光も消え、体に張り付くような重い闇があたり一面を覆い尽くす、そんな場所に墓地はあった。
墓地の敷地内にある管理棟の一角が僕の住み込み部屋だ。無論、家賃はタダ。その代わり、墓石にあげられたお供え物を下げたり、墓地内の草むしりをしたり、墓参りに来た人にお茶を出したりするのが僕の仕事だった。
友人は口を揃えて、「怖くないのか?」と聞いてくる。
しかし、僕には何が怖いのかよくわからなかった。清浄で静かな時間が流れる、この環境は僕にとって快適だった。好きな本もゆっくり読めるし、お供物として届けられるお饅頭やら煎餅やら、食べ物にも不自由はしなかった。上京したてでお金もない僕にとっては願ったり叶ったりだった。
何かが見える。何かを感じる。そんな不思議な体験は一切なく、年月は淡々と過ぎていった。
ある日のこと。
敷地のあちこちに伸びっぱなしになっていた雑草を取っていると、黙々と墓石の掃除をしている、ひとりの女性が目に入った。

「あのー、よろしかったら、後で管理棟にお立ち寄り下さい。お茶でも飲んでいって下さい」
と、その女性に声をかけた。驚いたように振り向いた女性は、
「はい、ありがとうございます」と、にこやかな笑顔で答えてくれた。
半時も経った頃。
先ほどの女性が、満足そうな笑顔をたたえ管理棟に顔をのぞかせた。
「なかなかお墓参りができなくて。本当に今日は来ることができて良かったです」
やさしい印象の、まだどこかあどけなさが残る、その女性は30代半ばくらいだろうか。お茶を飲みながら、ひとしきり世間話をすると、やがて、丁寧に頭を下げて帰っていった。
―気さくで感じのいい人だな。
―あんなに熱心に墓の掃除をするなんて、よっぽど大切な人だったんだろう。
夕方になり、僕は、お供え物を下げるため墓地を巡回することにした。墓にお供え物を添えたままにしておくと野良猫やカラスの格好のごほうびになってしまうのだ。
墓地の奥から順番に見回っていると、さっきの女性が掃除をしていた墓の前までやって来た。
時間をかけて掃除しただけあって、墓石はピカピカに磨き上げられていた。
故人が生前好きだったのだろう、ビールと煙草が供えられ、花入れには、真っ赤に美しく咲き誇ったアネモネが風に揺れていた。

ビールと煙草を下げようと墓石に手を伸ばすと、傍らに置いてあった飾り気のない白い封筒が目に入った。
「手紙か…」
お供え物のようにすぐに下げるのもはばかられ、そのままにして管理棟に戻った。
手紙は翌日も、そのまた翌日もそのままだった。
4日目の夕方、置きっぱなしにしておくのも忍びなく、手紙を下げることにした。
「死んだ人に書く手紙って何だろう。どんなことを書くのかな」
僕は手紙の中身が無性に気になり、いけないと思いながらつい、開けて見てしまった。
『私はあなたを死ぬほど憎んでいました。死んでくれてありがとう』
一瞬、頭が真っ白になった。
あの女性が…。
墓石に刻まれた男性の俗名に雨粒がポトリと落ちた。
熱心に墓石を掃除していたのは、憎むべき人がこの世からいなくなってくれた感謝の気持ちから出た行動だったのか。
恨みを抱えたまま生きている人の業の奥深さが妙に生々しく、ゾッとした。
数日後、墓地の庭で手紙を燃やした。
立ち上っていく煙が天に届かないうちに消えてしまうことを願って…
【その他の記事】
【第一話】ソープランド街の女
【第二話】夏の海
【第三話】格安の賃貸マンション
【第四話】踏切事故の落としモノ
【第五話】死期が見える男
【第六話】ドアスコープを覗いた先には…
【第七話】墓地の住人
【第八話】深夜の墓石の上に座るのは…